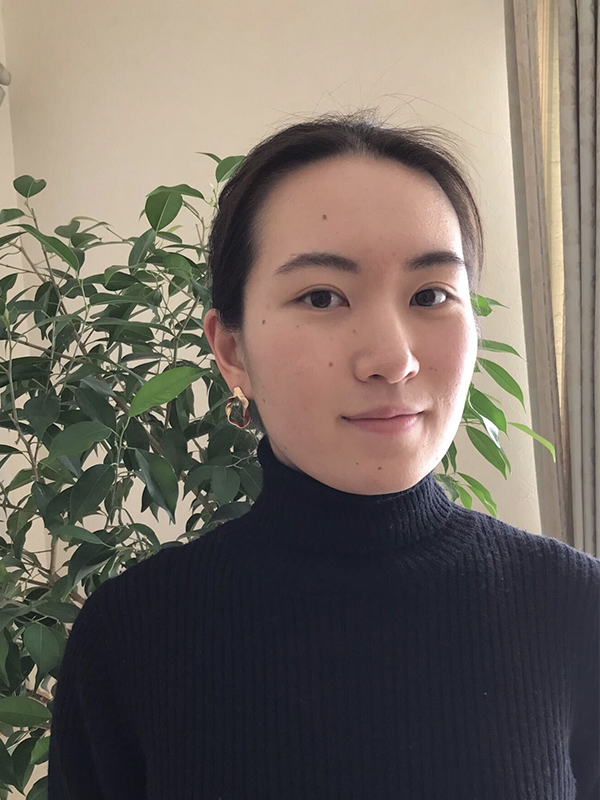ーー山口情報芸術センター(YCAM)で個展「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」を開催することになったきっかけや経緯を教えてください。
今回の展覧会は、2年ほど前の2023年にYCAM勤務の太田遥月さんからご連絡をいただき、1年かけてYCAⅯキュレーターの見留さやかさん、太田さんのお二人と展覧会プランを立ち上げました。私だけでなく、内部のお二人のご尽力があってこそ実現した展覧会だと感じています。YCAMは日本でも数少ないメディアアートに特化した施設なのですが、歴代のScopic Measureという企画で個展を開催されたアーティストの中では女性やクィアが非常に少なく、私自身もこのような機会をいただき大変光栄に思いました。

ーー展示に向けた準備や制作で、特に苦労されたことや工夫されたことがあれば教えてください。
まだあまり日本で大きく議論されていないクィア・エコロジーという領域を紹介するにあたり、どのように丁寧に議論の場を育むかということを何度もYCAMの皆様と話し合いを重ねました。日本でこれまで女性やクィアに焦点を当てた展覧会では、アーティスト本人の性自認やセクシュアリティに光が当たるものが多く、それはそれで過渡期として重要であるものの、翻ってどのようにそれらが「別の形の」現実の捉え方に接続するのかという議論があまりされてこなかったと思います。「女性」や「クィア」が大文字のアイデンティティーとして括られがちななか、だからこそそうしたSituated-agencies (特定の状況に置かれた存在)が、いかにマジョリティと異なる批評的観点を提示できるのか、という点まで踏み込んで議論したいという旨をキュレーターの見留さんとお話ししていました。クィア・エコロジーという思想を受け継ぐ点では、今回の展覧会は化学物質を通した、水平な惑星的親族(キンシップ)の捉え方という点において、家父長的・ヘテロセクシュアルな遺伝子の継承とは別の捉え方を提示できたらと考えています。
YCAMにはプロダクションチームやインターラボの皆様だけでなく、エジュケーションチームがいらっしゃり、展覧会を見守ってくださるサポートスタッフさんと日々コミュニケーションをとってくださっています。アーティスト・トークの際に鑑賞者の方からいただいた質問も含め、展覧会を見守り育ててくださる皆様に囲まれ、共に迷ったり試行錯誤しながら展覧会を作っていけることに本当に感謝しています。

ーー慶應義塾大学から多摩美術大学へ編入し、その後、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート、そして現在はドイツのベルリン芸術大学で学ばれています。非常にユニークな経歴ですが、特にイギリスやドイツでの留学経験から、「これは役に立った」「やっておいて良かった」と感じることはありますか?
自分と性別や人種、セクシュアリティが異なる人々に囲まれて生きるのが日常の世界のなかで、相手を敵か味方かの二項対立で判断せず、そこにあるスペクトラムを注視すること、また対話を諦めないよう努力することを学びました。ロンドン、ベルリンでは、フェミニストやクィアのコミュニティーに出会い、それらをとても嬉しく感じているものの、人種差別については、信頼している友人がパレスチナ侵攻について関心を示さなかったり、”I dont see color(私はあなたことを有色人種だと思っていない、だから私は差別主義者ではない=同時にあなたの差別の経験も認識できない)”といった根強いホワイト・フェミニズムの言説を投げかけられ、我を忘れるほど悲しみや怒りを感じることもありました。そうした際に、自分の過去のトラウマを相手に投射するではなく、一度冷静になって、相手が自分の話を聞く状態にあるかどうか、そうした努力をできる精神状態に自分がいるかどうかを丁寧にチェックし、時間をおいて話し合いを続けられるように心がけるようになりました。女性としてクィアとして、ケアの役割を担わされることを拒否したくなる衝動もありましたが、展覧会のテーマの通り、「ケア」と「親密さ」や「親密さ」と「毒性」は表裏一体のように思います。こうした態度の習得は、これほど分断が大きい世の中において、自分と異なるインターセクションにある人の声に耳を傾け、尊重しあえる関係を構築するうえで重要だと考えています。
ーー過去の活動や勉強、人との関係などの中で、現在のご自身につながっていると感じることがあれば教えてください。
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート在学中は、自身もクィアであり、薬物常用者であり、トラウマを抱えながら制作を続けたアレクサンダー・マックイーンに傾倒していた時期もあり、彼の人生から「痛み」や「アブジェクション(=拒絶されるもの)」について思索を深めました。なかでも彼の初期のコレクションである『Highland Rape』と呼ばれるランウェイは、イギリスによる、彼自身の出身であるスコットランドの植民地支配や、その過程で起こった女性への性暴力を題材としたもので、そこで沸き起こった激しい賛否両論も含め、現実の「出来事」に対する真摯な制作とは何か、眼差しの暴力、制作と翻訳の距離についても考えるきっかけを与えてくれました。それからフェミニスト・ニュー・マテリアリズムという文脈では、京都芸術センターにてキュレーションした「Ground Zero」という展示でトークゲストを務めていただいて以来親交のある、Forensic ArchitectureチェアのSunsan Schuppliの『Material Witness』という本に大変強い影響を受けたほか、Jesse Darling、Laure Prouvostといった作家にも影響を受けています。
加えて、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでWhiskey Chowというクィア・アーティストである恩師に出会い、2年間制作に伴走してもらう中で、「客体としてのクィアに「ついて」」ではなく「クィアの視点から」「クィアの経験を通して」制作を行う態度を学んだこと、Tai Shaniというターナー賞受賞作家の講師から、現実の複雑さを省略せずにアクティヴィズムと制作を相互に生かすことを教わったこと、多摩美術大学にて小田原のどかさん、久保田晃弘さん、永田康祐さん、谷口暁彦さん、クワクボリョウタさんという素晴らしい講師に恵まれたこと、どれも本当にかけがえのない経験です。

ーー今後、展示の機会を目指す方々や、同じ道を志す人たちへ、アドバイスやメッセージがあればお願いいたします。
私はまだまだ駆け出しのアーティストで、美術の道を志したいと思ったのも比較的遅く、一般大学を中退してから美大に編入し、留学し、今にいたるまで必死に活動を続けていたら、あっという間に時間が過ぎてしまったという感覚があります。ですが、この活動は必ずしも制作だけでなく、大学内でジェンダー平等を求める運動を起こしたり、批評誌を創刊したり、ドイツでデモに参加して拘留されたり、パートナーと大喧嘩したり、アクティヴィストに会いに足を運んだり、他の作家にインスパイアされて展覧会を企画したりなど、私を囲むあらゆる社会的な活動が、いまの私に繋がっていると考えます。展覧会の成功・失敗といった評価は、時代や価値基準によって激しく移り変わるものですが、こうした社会との繋がりによって導かれた「自分が制作をする理由」は、そうした流動性から一定の強度を持って自分を守ってくれるものだと思っています。もしこれから美術の道を志す方でこのインタビューを読んでくださっている方がいらっしゃいましたら、(頼りないながら)心から応援しています。
マヤ・エリン・マスダ個展:「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」
会期:2025年7月5日(土)〜2025年11月2日(日) 10:00~19:00 火休館
場所:山口情報芸術センター スタジオB
関連情報:
Tokyo art Beat インタビュー記事
マヤ・エリン・マスダ(増田摩耶)
2017年 慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科
2019年 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 編入学
2021年 BA 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース
2021年 ロイヤル・カレッジ・オブ・アート
2023年 ベルリン芸術大学
2026年度リクルートスカラシップアート部門エントリー受付中(締切:2025年9月16日)
募集要項はこちら⇗