江副記念リクルート財団は、2025年8月8日に東京で恒例の交流イベント”Meetup Reclabo”を開催しました。世界各地で学ぶ財団生が一堂に会するこの貴重な機会には、アート・学術部門から27名の学生が参加。普段は世界各国の拠点で活動し、直接会う機会は少ない財団生同士が、部門の垣根を越えて交流を深め、新たな関係性を育みながら、気づきを得る場となりました。本レポートでは、そのハイライトをお届けします。
基調講演 林千晶様
午前のメインプログラムは、現在アート部門選考委員を務める林千晶さん(株式会社 Q0 代表取締役社長/株式会社 ロフトワーク共同創業者・相談役)による基調講演。これまでのキャリアを通して捉えてきた「未来の兆し」について、お話しいただきました。
具体的なトピックスとしては、現在取り組んでいるプロジェクトをもとに、地方創生の取り組みや林業・建築・デジタル技術の連携事例、ご自身のバックグラウンドを活かしたアカデミアとビジネスの橋渡しを行うキャリアの考え方など多岐に渡ります。
午後の部で予定されたグループワークのテーマ“2045年、何が「当たり前」になっているか?”に向けたインプット機会も兼ねていたことから、財団生からは講演を通じて得られた視点や問いを起点にさまざまな質問や議論が起きました。


成果発表① 学術部門48回生 原野新渚 「イオンチャンネルから紐解く神経疾患のメカニズム」
2023年にコロンビア大学を卒業後、米国ニューヨーク大学 神経科学博士課程に在籍する原野新渚さんからは、現在取り組む「アルツハイマー病におけるカルシウムチャンネルの機能異常に関する研究」について発表しました。
また、財団の奨学生に採択されてからの6年を通じて、どのようにして研究対象の関心やキャリア観が変化したかについても言及。当初は宇宙医療に興味を持っていたが、現在は神経科学の基礎研究に取り組むようになった経緯を語りました。将来的には基礎研究で得た知識を応用して、宇宙医療や他の疾患研究にも貢献したいという展望を語りました。発表後の質疑応答では、イオンチャンネルの異常と疾患の因果関係や研究アプローチについて具体的な質問が挙がりました。

成果発表② 学術部門49回生 李為達「大型言語モデル(LLM)の研究活動報告」
2025年にコロンビア大学を卒業後、プリンストン大学博士課程に在籍予定の李為達さんが、現在取り組む「AI・機械学習分野」の研究について発表しました。
前提となる機械学習の歴史的背景から説明し、現代の言語モデルがどのように機能するか、特にインコンテキスト学習のメカニズムや、AIの安全性に関する研究について詳しく説明しました。今まさに世間の注目度が高いAIの各タスクにおけるバイアスの問題とその改善方法についても言及。質疑応答では、AIの研究に取り組む奨学生たちから研究テーマの選び方についてや、AIの安全性確保の方法について質問があり、活発な議論が起きました。

成果発表③ アート部門53回生 富田ネオ「通語的なもの」
2023年より、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校のファインアート学科で3Dを専攻する富田ネオさんが、自身の芸術観と実践について発表しました。
自身が芸術作品を「固有の表現であるかどうか」という観点からまなざし、時間軸的思考ではなく多様性軸的思考で芸術を捉えることで自身の美的倫理に対して意識的になることについて説明。また、「ひたすらなる」という概念や「通語技術(Jargonics)に関する自身の研究について紹介しました。質疑応答では、美的感覚の変化や芸術の新規性について議論され、特に学術部門の奨学生からは「一見捉えにくい芸術というものに対して見方を養えて勉強になった」との声が挙がりました。
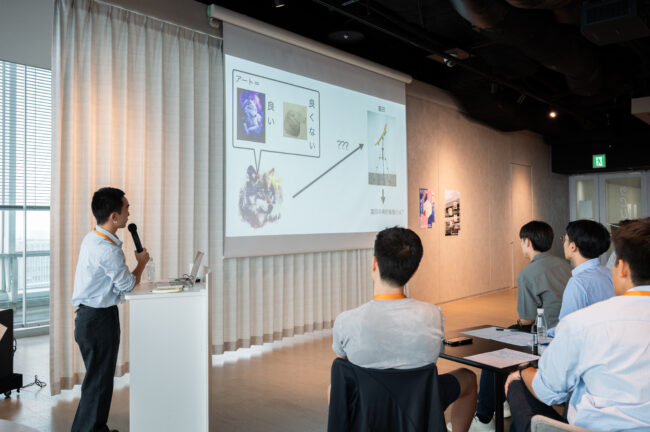
グループワーク
今年のテーマは「2045年に何が当たり前になっているか?」。テーマ設定の背景には、各領域での最先端の研鑽を通じて未来をどう見立てるか、という観点に学生たちの意欲が高かったこと、また2045年は「人工知能(AI)が人間の知能を超えるシンギュラリティが到来する」と言われていることから、予測不可能な社会影響を議論するうえでも適した議論スコープであったためです。このテーマについて、学術部門・アート部門混成のグループで議論を行いました。
最終発表では、各グループが2045年の「当たり前」について、前提条件(制度・インフラ・文化)まで含む社会モデルとして構想し、具体的な実現ロジック(どのような変化で成立するか)を整理。「移民受け入れと多文化社会の制度・デザイン」、「AI時代の教育と、”頭を使う”体験の再設計」、「多様化が加速する社会で、自分で共同体を選べる制度・インフラへの変容」、「”就活化”する2045年の大学入試」といった多岐に渡るモデルが発表されました。




閉会挨拶
最後は、代表理事理事長の峰岸真澄の閉会挨拶で締めくくりました。
リクルートスカラシップは、日本人が世界でずば抜けた活躍を期待される分野でトップを狙う人材を主な対象として支援しています。毎年、その各領域のトップ人材が懇親を深める機会を提供しており、今年度は、例年の各部門のMeetupイベント、器楽部門のスカラシップコンサートに加え、アート部門の展覧会を開催。奨学生には、まず研究・制作活動に没頭し成果を出し、その後こうしたネットワークを活用して、自身の専門領域と社会をつなぐことや、海外と日本の橋渡し役として活躍されることを期待していると締め括りました。







