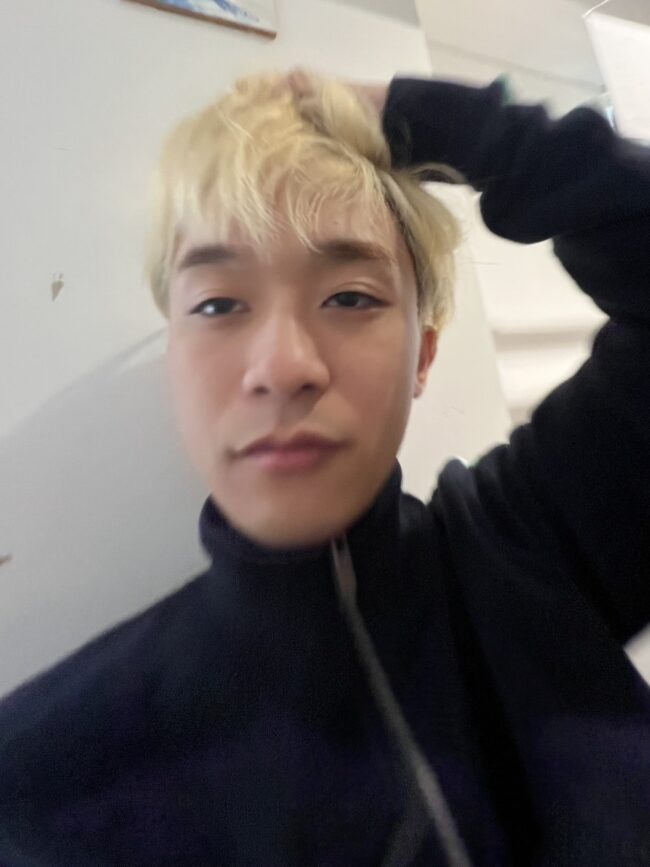私は18歳になってすぐに、ロンドン芸術大学のファンデーションコースに入学しました。その後の学部三年間を通してファインアート専攻に在籍し、ファインアートの世界にどっぷり浸ることができました。当初、私は作品制作をプロフェッショナルなキャリアとして行い生計を立てていくというスタンスでしたが、この4年間で得たさまざまな経験と変遷を活かし、今後は柔軟性を持ってアートという領域と関わっていきたいと思うようになりました。
この4年間のうちに、私にとっては人生を左右する決定的な出来事がいくつもありました。またこの4年で、自分が日本にいたころ見ていた世界や考え方が思い出せないほど、自らの価値観や認知世界は目まぐるしく変化したと感じています。

ある本に、パークという都市社会学者が提唱した「マージナルマン」という言葉が出てきました。マージナルマンは日本語に訳すと「周辺の人」という意味で、二つ以上の異なる社会的集団や文化の間にいてどちらにも完全に属せない立場の人のことを指すそうです。私が大学生活を通じて最も強烈に自覚したことは、自分がこの「マージナルマン」であるということだと思います。例えば、ヨーロッパではOKとされていることが日本では全く通用しない、もしくは規範から外れているといったことは幾千とありますし、逆も然りです。つまり、何が普通で、何が普通ではないのか—規範、ルール、マナー、話し方、ユーモア、センスにいたるまで—が日本とヨーロッパではまるで違いますが、そのどちらも自分の中に完全には収まらず、常に日本とヨーロッパとの間の、どちらでもないどこかを彷徨い続けているように感じることが多いです。私の居場所は一体どこにあるのか。イギリスに来てからの4年間、特定の規範の中に収まりきらない、マージナルな私という個体の抱える極めてユニークな経験や問題のそのあまりのユニークさに、葛藤を感じました。

もう一つ単語を出しますが、バイリンガリズム研究で使われる「multi-competence」という概念があります。この言葉は、簡単に言うと、バイリンガルやマルチリンガルの人は、単に「A言語」と「B言語」という2つの言語能力を持つだけでなく、その2つが相互作用して新しい認知世界や言語スキルを作り出す、という考え方らしいです。例えば、英語と日本語を話す人は、英語の能力と日本語の能力を別々に持つのではなく、それらが相互に影響し合いながら、ひとつの複合的なシステムを形成しているという見方です。自分自身はバイリンガルと名乗るには程遠い英語力ですが、4年間は英語をメインで使いました。その中で、日本語がきちんと使えなくなることもあれば、反対に英語も完璧ではないので、日本語と英語をごちゃまぜに喋るのが自分にとって自然に感じるということが起きたりします。
さて、「マージナルマン」と「multi-competence」という概念を例に出しましたが、これらに対して、どちらも未熟で中途半端なだけだ、と切り捨ててしまうことは簡単です。一方で、それをむしろ「どちらでもない立場」に立つことができる、特別な視点や可能性を秘めているのではないかとも感じます。グローバル化が進んだこの世界で、こうした両義性や矛盾を自分の中に内包することは、まだ見たことのない、私の知らない他者の存在を認め、自分の理解の範疇にないものへの拒絶反応を和らげ、想像力と尊重を持って他者に向き合う姿勢を与えてくれる大切な価値観だと信じています。

この4年間は、本当に経済の変動の激しい時代でもありました。覚えている方も多いと思いますが、特に2023−2024年にかけては日銀が何度も市場介入し、輸入品価格の高騰が叫ばれるなど、ニュースをつければ円安の話ばかりでした。留学先にかかわらず多くの日本人留学生にとっては死活問題になるような苦しい時間だったと思います。加えてイギリスでは留学生に対する学費の大幅な値上げ、ロンドン中心部の家賃の高騰、いわゆるCost-of-living crisis(生活費の危機。インフレによる物価の上昇などが社会問題となった)などが重なり、経済的にも精神的に堪える経験をしました。
そんな中、江副記念リクルート財団が外貨建てで奨学金支給を開始してくれたことは、経済的にも精神的にも非常に大きな助けとなりました。外貨でいただけることで、コンバートの手数料とレートの影響で目減りしてしまうということがなくなりました。また日本円でもらうと、どうしても日本での物価感覚で物事を考えてしまい「なんでこんなに高いの」と出費するたびに精神をすり減らしていましたが、外貨でもらえることでそのような心理的な負担も軽減しました。現地通貨で奨学金をもらえることで、日々の生活に対するストレスを少しでも減らすことができました。特に留学という大きな挑戦をしている中で、生活の心配が少しでも軽くなることで、学業や新しい出会いにより集中できるようになったと思います。
さらに、こうした奨学金の支援は単に経済的な助けになるだけでなく、「あなたは価値がある」というメッセージのようにも感じられました。どんなに苦しい状況でも、自分の選択が尊重され、支援されているという実感があったからこそ、最後まで踏ん張れたと思います。本当に江副記念リクルート財団さまのお力抜きでは到底実現しなかった留学経験だったと思います。この場を借りて、心から感謝の気持ちをお伝えしたいです。ありがとうございました。

これから留学したいと考えている人へのメッセージ:
国によって差はありますが、総じて留学というのは安い買い物ではありません。多くの国では日本のように安くて美味しい食事はないですし、日本のように居心地の良く過ごすことも難しいかもしれません。電車がストライキで来なかったり、エアコンがなかったり、コンビニも自販機もありません。海外に対して抱いていたイメージと実際とのギャップに落胆することもあるかもしれません。でも、私は留学を経験できて本当に良かったと心から思えます。
自分は人生における「子どもから大人になる」重要な過渡期を日本の外で過ごしました。子どもとしての若さ、甘え、そして大人としての自覚、責任感の2つが自分の中で混沌と移り変わっていくのを感じたのも、あるいは自分の誇るべき功績や得意なことを見つけたり、逆に失敗や苦い後悔を経験したのも、思えば全て留学中でした。その意味で自分にとってこの留学は、自分の専門分野の学び以上に、等身大の自分自身を見つめて人間的な学びを得た本当に貴重な時間でした。
こんなことを言ったら留学する人が減るかもしれませんが(笑)、多くの場面で不快な思いや苦い失敗をすることにこそ、留学の本質があるのかもしれません。なぜなら、その不快さや葛藤の中で、自分が知らなかった価値観に触れたり、自分自身の思い込みに気づいたりするからです。日本にいるときには意識しなかったことが外に出ることで初めて見えてくる、といったこともたくさんあります。そしてその体験は、どんな人であれ、その人の価値観を大きく揺さぶるようなものになると思います。一人ひとりが多様でユニークな経験をし、いいことばかりとはいかないと思いますが、最後にはそれでも留学して良かったと思えるはずです。なので、ぜひ多くの人にチャレンジしてほしいと思います。自分は器用に生きられるタイプではないので本当に色々大変でしたが、それでもそのプロセスを経ることで、自分にとって本当に大切なものや、何がしたいのか、あるいは何をするのかを考え直す素晴らしい体験だった、と言うことができます。