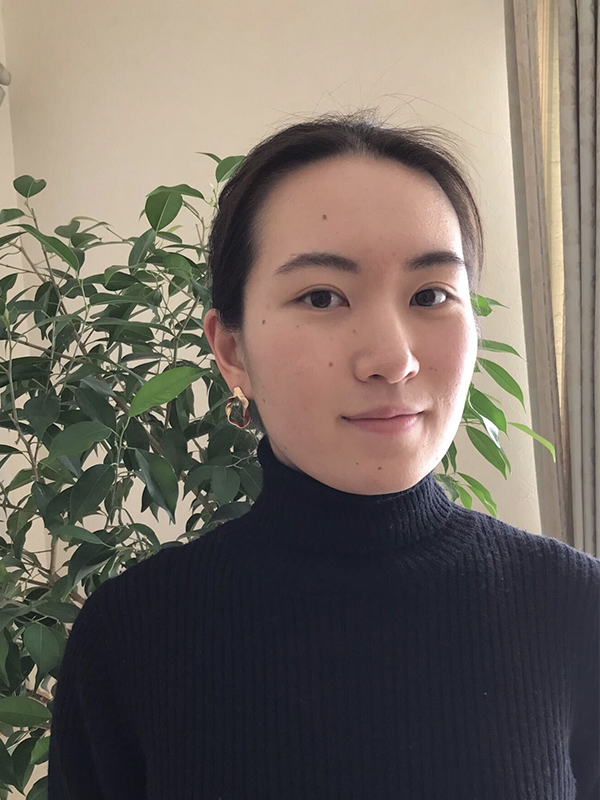卒業レポートを何から書き始めたらよいか、考え始めると難しいです。自らの意志で日本を離れイギリスで過ごした2年間の短さと長さを感じています。
勝手な時間とお金の使い方、奇特な毎月のレポートを許していただきありがとうございました。濃密なロンドンでの2年間は、財団の支援とアート部門の仲間がいなければ過ごせなかったと思います。確実に人生が変わったと言える時間でした。
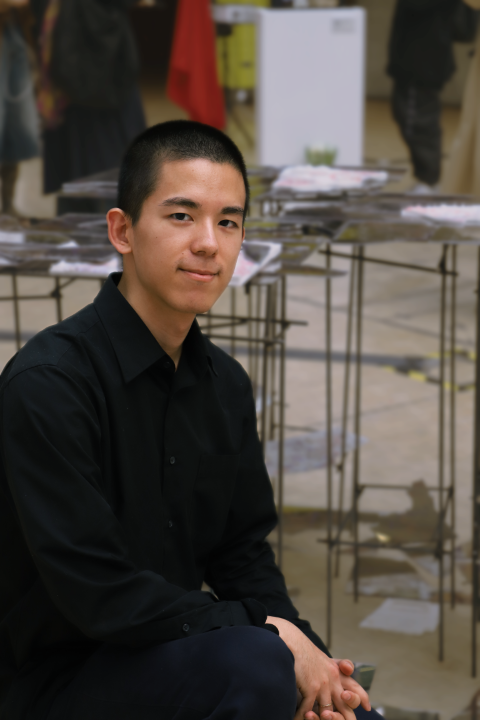
当初はとにかくロンドンでのアーティスト生活に必要な機会と条件を手にできればいいと思っていました。ロンドンには最高のチャンスとアーティストが存在していると思っていたからです。しかし今の私はそのような視点のナイーヴさとテイカー的マインドセットを笑います。アーティストと言っても普通の人間の1種類でしかないし、人はアーティストであると同時に、いやそれよりも前に、一人の共同体の一員であり、家族の一員であり、肉体と精神の有限性に基づいた瑣末な一つの塵でしかないからです。しかしその一粒の塵は、知覚と思考と想像と呼ばれるある種のふるまいにおいて他の塵とは少々異なるがために、アートなどという名前を自称します。しかしそれでいいのだと思います。自らの行為の取るに足らなさと同時に、それでも私にとっては価値があるのだという個体の信念が両立する時に、初めて私は生きた実感を感じます。このようなマインドセットに自分を変えてくれたという点でこの2年間で出会ったものごとに大きな意味があると思っています。
この分野はその道一本でプロのアーティストとして収入を得るのがきわめて難しい分野です。しかし、自らの確固たる幻想である作品世界一つだけに自身の経済的存在条件を明け渡すのは、実は大きな危険と隣り合わせであることを自覚しなければならないと思います。従来とは別の意味で同じアーティストという名前を訂正するのでないかぎり、それは外在的な職能に合わせて自らを型取りするのと同義です。可塑性を保ちつつも、それは特定のフレームにいつかはまるためではなく、自分自身を可変的フレームと定義するためであることを自覚すること。そのためにどれほどの実践と哲学とサイエンスが必要か、片鱗を覗いているからこそ痛切に感じます。常識的に考えれば、それはほとんど何をしているかわからない人でしかないからです。

それでも、私は他者の不可知性を強調しようとは思いません。連続性と連帯は共同展示やコラボレーションの経験によって作られます。ロンドンでは、インテリムショー、セントラル・セント・マーチンズのギャラリーでの展示、オルタナティブスペースでの展示や、オックスフォードの博士課程の学生との共同制作などを経験しました。毎回、交渉の大変さと、ギリギリの綱渡りの上でのみ成立する作品制作となりました。モノを作ることとその意味を作ることの同時性がどれほどの仕事を必要とするか、いつも新鮮な気持ちで発見しています。さらに2025年8~9月の「回帰観測展:リクルートスカラシップエキシビション」の実現のために必要なキュレーション、交渉と合意形成、自身の作品制作の経験は、私にゼロからの展示制作という大きな経験を与えてくれています。ゼロからものごとを作ることは大変ですが、その分極めて貴重で、財団との関わりがなければありえなかったことだと思います。これらの全てが、アーティストとしてというよりも人間としての成長につながっています。
これから財団の支援を受けるアーティストの方には、できるだけ他の奨学生と関わって連帯を作ってほしいと思います。日本にいようが海外にいようが基本的には孤独と独我論、私的言語や、逆に全体主義と対抗するという大きな困難のもとにいるのがアーティストだと思います。その一つのオルタナティブとして財団の奨学生というつながりは、きわめて不確かであるがゆえに強力にもなりうるものだと思います。似た道を歩もうとしている者の一人として陰ながら応援しています。