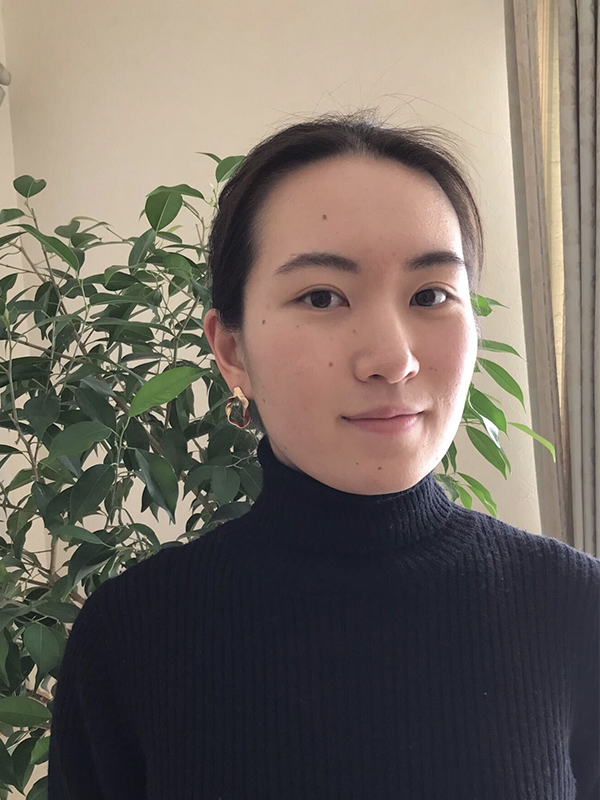もう一年が過ぎ、9月には新しい留学生たちが英国にやって来ました。私はもう学校に通う必要がなくなり、そのことに強い違和感を感じました。新しい顔ぶれを見ながら、羨ましいと思ったのは彼ら自身ではなく、むしろ初めてロンドンに降り立った頃の自分でした。あの頃はまだ学業のプレッシャーも少なく、全てが新鮮に見えていました。最近では、オックスフォード・ストリートに灯るクリスマスの天使のイルミネーションを見るのが怖くなりました。あの光は、私に「もう新鮮さは過ぎ去り、これからは現実の重さが待っている」と絶えず囁きかけているように感じられるからです。
2023年に英国の大学院に進学することが決まった時、同じく財団の奨学生である増田まやさんからこの奨学金制度の存在を教えていただきました。応募の準備をしていた当時の私は、自分の制作や将来に大きな不安を抱えており、「本当に自分はアーティストとしてやっていけるのか」と日々自問していました。同時に、家族に対しても、自分が本気で芸術に取り組み、その道で生きていけるのだということを証明したい気持ちが強くありました。
そのような状況のなかで採択の知らせをいただいたとき、胸の奥から大きな力が湧いてくるような感覚がありました。学部時代に最も信頼していた教授に報告すると、教授は「やっと家族の前で胸を張れるね。本当に良かった」と声をかけてくださいました。その瞬間、財団からいただいたのは単なる経済的な支援にとどまらず、自分の存在や選択を肯定してもらえたという精神的な支えでもあるのだと強く感じました。
ロンドンでの生活は決して容易ではありません。制作に必要な経費や生活費の負担は大きく、もし財団の助けがなければ、作品を構想する以前に日々の暮らしに押し潰されていたかもしれません。経済的な安心感があったからこそ、私は実験的な試みや挑戦的なテーマに取り組む余裕を持つことができました。
私は中国で生まれ、日本で学び、そして英国で制作を続けてきました。異なる文化圏をまたぎながら暮らす経験は、自分のアイデンティティに常に問いを投げかけてきます。国籍や在留資格といった制度は、私たちの存在を定義し制限する枠組みですが、その枠に完全に収まりきらない「間(はざま)」の経験こそ、私の制作の根幹となっています。国境を越える身体の感覚、制度と個人の摩擦、どこにも属しきれない存在の居場所。そうしたテーマは、ロンドンでの日常を通じて一層具体的に、そして切実に迫ってくるようになりました。
在学中には、《Breeding Migration》、《A Drawn Line》や《Tastes Like Paper》などのプロジェクトを展開し、展示や発表の機会を重ねました。海を越えて作品を運び、制度の文書を食べられる紙に印刷し、あるいは魚の皮に国境の痕跡を刻む――そうした行為は、単なる造形ではなく、制度と身体の関わりを観客に強く意識させる装置となりました。ありがたいことにいくつかの作品は賞をいただく機会にもつながりましたが、それ以上に大切だったのは、作品を通じて他者と「境界について語る場」を共有できたことです。
学生としての在留資格を失ったとき、私は「いかに合法的に英国に滞在し続けられるのか」という現実的かつ切実な問題に直面しました。生活と制作の基盤が一瞬にして揺らぐような不安定さのなかで、それでも作品を作り続ける意味を問い直さざるを得ませんでした。
しかし、そのような葛藤も含めて、私は「問いを持ち続けること」そのものが芸術の営みだと今は感じています。答えを提示するのではなく、制度に揺さぶられる身体や、可視化されにくい声なき存在をどう想像できるか――その姿勢を失わずにいたいと思います。
これからも私は、国境をめぐる矛盾や制度の不可視な暴力を見つめながら、そこに立ち会う人々と共に考える作品をつくり続けたいと思います。芸術にできることは限られているかもしれませんが、その限界を引き受けたうえで、社会とつながる小さな契機をつくることが、私にできる最大の役割だと信じています。

最後に、この二年間、変わらずに支えてくださった江副記念リクルート財団の皆さまに心より感謝申し上げます。そして、これから奨学生になる方々へ。どうか恐れに縛られず、どんどん踏み出してください。躊躇から生まれる後悔は、恐怖そのものよりも長く、深く心に刻まれてしまいます。だからこそ、未知を体験する勇気を持ってほしいのです。
大胆に楽しんでください。